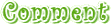interactiveに付設しているブログです。お仕事の事だけではなく、生活からの視点で、よろず文を書いています。
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アド
2025.12.04
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010.11.19
西高東低
気圧配置の事ではなくて、福祉事業の手厚さの事だ。児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、他の事を指す。今日、こども園の記事を見ていて何となく思い出した。
10年前から幼保一元化は保育学会等で、議論されていた事だが、遅々として進まず、もう暗礁に乗り上げたのだろうと思っていた(もうその時期しか私はご縁もなかったし)。
ここに来て、やっと認定子ども園が少し、現実的に機能し始めてきたようだった。
はっきり言って、現実の世界では、どちらも小さな子どもの保育と教育をしているのでダブる事を多くやっている。だが、理論的には大きく違うし、現実的に管轄している省庁の意見も違うので相容れない感じだった(その頃は)。
どちらも補助金などをもらって運営しないと、とても運営できない位の厳しさが保育園や幼稚園(有名幼稚園は除く)にはある。なので、そこを管轄しているお役人の言う事を聞かないといけないし。。。という状況だったように記憶している(一応保育所保育指針や幼児教育指導要領だっけ?あれも読んだけど忘れた)。
役人も学者も現場のトップの人も、視座や視野(見ている所)、重要だと思っている所が違う様に感じる。
じきょう(児童教育学部)に通っていた若い女の子が、「私は教育学を学んでいるので、じがく(児童学部)の保育士がやっている事は世話で、あれは教育ではないですから」と言い切っていた(じきょうの人は小学校か幼稚園の教員免許を持っている)。
おむつを替えたり、ミルクをあげたりする作業の中にも、発達心理学も教育学も広義の意味では含まれているんだけどね。。。そうは学者は教えていないんだろうねぇ。恐ろしい事だとその当時思いましたもん。
そういう事とは、関係なく、現場は西高東低で、児童福祉(言うまでもないが障害者福祉も)と思い出していた。地縁、血縁がまだ存続しているのかもしれないね、関西の方が。。。
まとまらないなぁ。。。でも、今日はおしまい。
10年前から幼保一元化は保育学会等で、議論されていた事だが、遅々として進まず、もう暗礁に乗り上げたのだろうと思っていた(もうその時期しか私はご縁もなかったし)。
ここに来て、やっと認定子ども園が少し、現実的に機能し始めてきたようだった。
はっきり言って、現実の世界では、どちらも小さな子どもの保育と教育をしているのでダブる事を多くやっている。だが、理論的には大きく違うし、現実的に管轄している省庁の意見も違うので相容れない感じだった(その頃は)。
どちらも補助金などをもらって運営しないと、とても運営できない位の厳しさが保育園や幼稚園(有名幼稚園は除く)にはある。なので、そこを管轄しているお役人の言う事を聞かないといけないし。。。という状況だったように記憶している(一応保育所保育指針や幼児教育指導要領だっけ?あれも読んだけど忘れた)。
役人も学者も現場のトップの人も、視座や視野(見ている所)、重要だと思っている所が違う様に感じる。
じきょう(児童教育学部)に通っていた若い女の子が、「私は教育学を学んでいるので、じがく(児童学部)の保育士がやっている事は世話で、あれは教育ではないですから」と言い切っていた(じきょうの人は小学校か幼稚園の教員免許を持っている)。
おむつを替えたり、ミルクをあげたりする作業の中にも、発達心理学も教育学も広義の意味では含まれているんだけどね。。。そうは学者は教えていないんだろうねぇ。恐ろしい事だとその当時思いましたもん。
そういう事とは、関係なく、現場は西高東低で、児童福祉(言うまでもないが障害者福祉も)と思い出していた。地縁、血縁がまだ存続しているのかもしれないね、関西の方が。。。
まとまらないなぁ。。。でも、今日はおしまい。
PR

 管理画面
管理画面