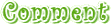interactiveに付設しているブログです。お仕事の事だけではなく、生活からの視点で、よろず文を書いています。
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アド
2025.12.14
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010.11.06
発達障害大学生支援への挑戦
ご紹介頂いた本を読んでみた。
発達障害大学生支援への挑戦ーナラティブアプローチとナレッジマネジメントー
斉藤清二ほか 金剛出版
1■二項対立を超える(p88から引用)
「発達障害の専門家と非専門家を相補的な関係として捉えている。発達障害の専門家の支援のみによって成立するのではなく、一般の教職員の支援があってこそ成り立つとの認識の下で、この両者の連携関係をマネジメントによって成立させる事を大きな目標としている」
2■合理的配慮の基本的な考え方(p112)
「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、すべての人権および基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要、かつ適切な変更および調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」
「特定の場合」の意味
「他の者との平等」を示すコンセプト
「必要かつ適切な変更及び調整」の判断と具体化
「配慮を行う者の不釣合いな又は過重な負担」
3■コミュニケーション教育法(p237)
「趣味やこだわりの世界を共有して人との関係性を築くという方向性は、コミュニケーションを活性化させるために、非常に有効な手法だと思われる」
4■ナラティブアプローチとナレッジマネジメント(p248〜249一部、引用)
ナレッジマネジメント理論≒トータルコミュニケーションサポート論(TCS論)+経営学で、なお、TCS論≒発達障害だけでなく、コミュニケーションに困っている人の支援の事。経営学における経営(マネジメント)とは「人を動かして構想を実現すること」。組織とは「少なくとも1つの明確な目的のために2人以上の人々が恊働すること」だ。人的資源管理論では、従業員のパフォーマンスを向上させ、能力を最大限に生かすことであり、研修(off the job training)のみならず、実習(on the job training)が必要だ。
以上が気になった所で、付箋が付いていた所だわ。
1は最もなご意見なんだけど、現場でやってみるとすごく難しいと実感している。コミュニケーションが得意な人から見ると、そうでない人は理解しにくいし、その逆も然りだからだ。
2は合理的配慮自体は、非常に重要で、ぜひ採択?されてほしい内容ではある。が、これを現場で行う人は、非常にバランス感覚の良い人でないと判断が難しいので、既存の専門職(マニュアルに従って動いている人達)では出来ないのでは?と思った。
3はナラティブアプローチの中の、コミュニケーション教育法の所だが、大切だと思う。パーソナリティ障害や発達障害関係のクライエントには、これに付き合わないと効果は乏しいと思いますもん、経験上。。。
4はへ〜そうなんだと思う事が多い項目だった。だけど、現実的には当たり前の理論かなぁと。でも、企業勤務経験が数年以上ある私が読むからかもしれないけど。
って言う感じかしら。。。専門書の割には、読みやすい本で、お勉強になりました。
発達障害大学生支援への挑戦ーナラティブアプローチとナレッジマネジメントー
斉藤清二ほか 金剛出版
1■二項対立を超える(p88から引用)
「発達障害の専門家と非専門家を相補的な関係として捉えている。発達障害の専門家の支援のみによって成立するのではなく、一般の教職員の支援があってこそ成り立つとの認識の下で、この両者の連携関係をマネジメントによって成立させる事を大きな目標としている」
2■合理的配慮の基本的な考え方(p112)
「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、すべての人権および基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要、かつ適切な変更および調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ不釣合いな又は過重な負担を課さないものをいう」
「特定の場合」の意味
「他の者との平等」を示すコンセプト
「必要かつ適切な変更及び調整」の判断と具体化
「配慮を行う者の不釣合いな又は過重な負担」
3■コミュニケーション教育法(p237)
「趣味やこだわりの世界を共有して人との関係性を築くという方向性は、コミュニケーションを活性化させるために、非常に有効な手法だと思われる」
4■ナラティブアプローチとナレッジマネジメント(p248〜249一部、引用)
ナレッジマネジメント理論≒トータルコミュニケーションサポート論(TCS論)+経営学で、なお、TCS論≒発達障害だけでなく、コミュニケーションに困っている人の支援の事。経営学における経営(マネジメント)とは「人を動かして構想を実現すること」。組織とは「少なくとも1つの明確な目的のために2人以上の人々が恊働すること」だ。人的資源管理論では、従業員のパフォーマンスを向上させ、能力を最大限に生かすことであり、研修(off the job training)のみならず、実習(on the job training)が必要だ。
以上が気になった所で、付箋が付いていた所だわ。
1は最もなご意見なんだけど、現場でやってみるとすごく難しいと実感している。コミュニケーションが得意な人から見ると、そうでない人は理解しにくいし、その逆も然りだからだ。
2は合理的配慮自体は、非常に重要で、ぜひ採択?されてほしい内容ではある。が、これを現場で行う人は、非常にバランス感覚の良い人でないと判断が難しいので、既存の専門職(マニュアルに従って動いている人達)では出来ないのでは?と思った。
3はナラティブアプローチの中の、コミュニケーション教育法の所だが、大切だと思う。パーソナリティ障害や発達障害関係のクライエントには、これに付き合わないと効果は乏しいと思いますもん、経験上。。。
4はへ〜そうなんだと思う事が多い項目だった。だけど、現実的には当たり前の理論かなぁと。でも、企業勤務経験が数年以上ある私が読むからかもしれないけど。
って言う感じかしら。。。専門書の割には、読みやすい本で、お勉強になりました。
PR

 管理画面
管理画面