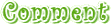interactiveに付設しているブログです。お仕事の事だけではなく、生活からの視点で、よろず文を書いています。
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アド
2025.11.21
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010.10.17
ソーシャルスキルと職業性ストレス
産業カウンセラー関係の雑誌に目を通していた。あら、衣川(東関東支部の)さんの記事が載っていると思ったら、読書案内だった。
ソーシャルスキルと職業性ストレスー企業従業員の臨床社会心理学的研究ー
田中健吾著 晃洋書房
一部を引用する(産業カウンセリング 2010.10 #277)。
「企業従業員の職場適応の見地からSSを捉えると、新たな関係をいかに構築し、深化させるというよりも、現有社員という限られた範囲内で、いかにコミュニケーションをとり企業内で付与された役割に応じた業務を行うか、あるいは人事管理や人材配置を行うかあるいは対人的処理を行うかが重要である。
ところで、心理的ストレス/プロセスに代表される不適応状態の発生や維持について、近年はサブタイトルにあるように臨床社会心理学の分野が注目されつつある。社会心理学が「状況/環境」の普遍的な影響力を中心に検討し、臨床心理学が一貫した「個人差/個別性」を検討してきたのに対して、臨床社会心理学は「臨床的問題を視野にいれつつ、社会心理学原理の応用可能性を探求する分野」として定義される。
こうした臨床社会心理学分野での心理的援助方策における不適応状態の理解において、人間関係や対人的相互作用に関する社会心理学的要因の影響の重要性が、強調されるようになったである。
現在、企業集団で実際に導入されており、エビデンスに基づいた行動科学的手法によってその効果が明らかにされているSSの教育には、積極的傾聴法、自己主張訓練等単発のSS(ソーシャルスキル)教育が多く、「主張」と「傾聴」のバランスや上司と部下のマネジメントといったトータル的な社員教育プログラムがないことも、今後の検討すべき課題である。
これまでSSが、心理学的職場ストレス/プロセスを構成するどの要因にどのような影響を与えているかに関して精査されてこなかったことを考慮すると、特にコーピングとSS(コーピングと個人的資源としての)を明確に区別した教育手段が有効であることが、本研究で明らかにされている」
だそうだ。
まあ、そうね、臨床心理学も臨床発達心理学も応用心理学の一流派なので、社会心理学の枝別れが、臨床社会心理学なんでしょう。人間の集団心理(一般心理)だけでは説明が付かない事は多い。だけど、臨床心理学的に、個別に分析/対応だけでは、どうにもならない事も多い。集団主義的な国なので、集団の心理の分析は大きい。でも、それも一筋縄ではいかない。
Aセクションでは、変わった人でも、Bセクションでは、普通の人。
とか。
A部長には、バカ者と言われるが、B部長には、面白くて可愛い奴と言われたりする現象じゃないかしら。。。。
ちょっと、読んでみようかしら。
ソーシャルスキルと職業性ストレスー企業従業員の臨床社会心理学的研究ー
田中健吾著 晃洋書房
一部を引用する(産業カウンセリング 2010.10 #277)。
「企業従業員の職場適応の見地からSSを捉えると、新たな関係をいかに構築し、深化させるというよりも、現有社員という限られた範囲内で、いかにコミュニケーションをとり企業内で付与された役割に応じた業務を行うか、あるいは人事管理や人材配置を行うかあるいは対人的処理を行うかが重要である。
ところで、心理的ストレス/プロセスに代表される不適応状態の発生や維持について、近年はサブタイトルにあるように臨床社会心理学の分野が注目されつつある。社会心理学が「状況/環境」の普遍的な影響力を中心に検討し、臨床心理学が一貫した「個人差/個別性」を検討してきたのに対して、臨床社会心理学は「臨床的問題を視野にいれつつ、社会心理学原理の応用可能性を探求する分野」として定義される。
こうした臨床社会心理学分野での心理的援助方策における不適応状態の理解において、人間関係や対人的相互作用に関する社会心理学的要因の影響の重要性が、強調されるようになったである。
現在、企業集団で実際に導入されており、エビデンスに基づいた行動科学的手法によってその効果が明らかにされているSSの教育には、積極的傾聴法、自己主張訓練等単発のSS(ソーシャルスキル)教育が多く、「主張」と「傾聴」のバランスや上司と部下のマネジメントといったトータル的な社員教育プログラムがないことも、今後の検討すべき課題である。
これまでSSが、心理学的職場ストレス/プロセスを構成するどの要因にどのような影響を与えているかに関して精査されてこなかったことを考慮すると、特にコーピングとSS(コーピングと個人的資源としての)を明確に区別した教育手段が有効であることが、本研究で明らかにされている」
だそうだ。
まあ、そうね、臨床心理学も臨床発達心理学も応用心理学の一流派なので、社会心理学の枝別れが、臨床社会心理学なんでしょう。人間の集団心理(一般心理)だけでは説明が付かない事は多い。だけど、臨床心理学的に、個別に分析/対応だけでは、どうにもならない事も多い。集団主義的な国なので、集団の心理の分析は大きい。でも、それも一筋縄ではいかない。
Aセクションでは、変わった人でも、Bセクションでは、普通の人。
とか。
A部長には、バカ者と言われるが、B部長には、面白くて可愛い奴と言われたりする現象じゃないかしら。。。。
ちょっと、読んでみようかしら。
PR

 管理画面
管理画面