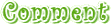interactiveに付設しているブログです。お仕事の事だけではなく、生活からの視点で、よろず文を書いています。
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
ブログ内検索
最古記事
P R
忍者アド
2025.11.30
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2011.11.06
キャリア教育その2
それで、進路指導が上手くいく生徒というのは。。。。
進路希望の決定において、偶察力(serendipity/セレンディピティ)がある事が多いという。決定するまでの1〜2年の間、色々な勉強や体験をする事になるのだが、その日々の積み重ねの中から、ある日突然、偶然の産物が発生する。それがセレンディピティとなり、決定に至るのだそうな。
なるほど。
企業での商品開発の例をたとえに挙げていたが、分かりやすかった。ポストイット(ふせん)は偶然の産物だったらしい。現実に開発していたのは「強い接着剤」だったようだが、セレンディピティだったのは「弱い接着剤」を使った、便利な事務用品「ふせん」だったのだろう。
そんな「気づき」の様な、発見が、やはり進路決定には必要な様だった。
進路希望の決定において、偶察力(serendipity/セレンディピティ)がある事が多いという。決定するまでの1〜2年の間、色々な勉強や体験をする事になるのだが、その日々の積み重ねの中から、ある日突然、偶然の産物が発生する。それがセレンディピティとなり、決定に至るのだそうな。
なるほど。
企業での商品開発の例をたとえに挙げていたが、分かりやすかった。ポストイット(ふせん)は偶然の産物だったらしい。現実に開発していたのは「強い接着剤」だったようだが、セレンディピティだったのは「弱い接着剤」を使った、便利な事務用品「ふせん」だったのだろう。
そんな「気づき」の様な、発見が、やはり進路決定には必要な様だった。
PR

 管理画面
管理画面